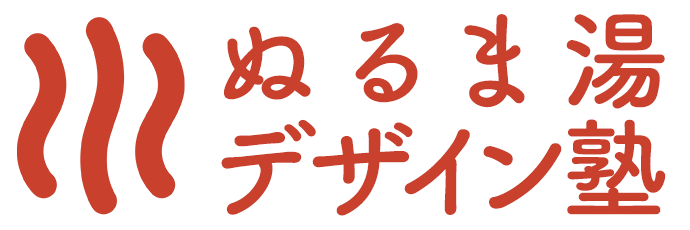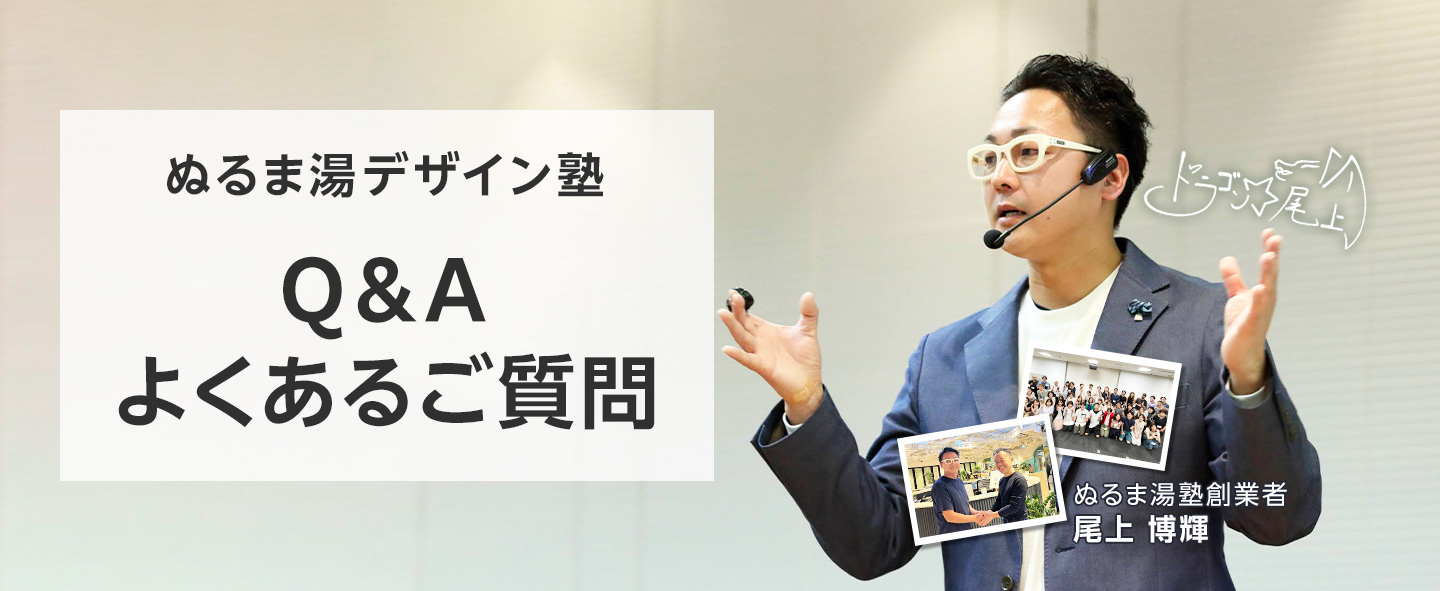
Webデザイン5日間チャレンジDay4でぬるま湯デザイン塾について数多くのご質問が届いておりますので、ここでお答えしておきます。
![]() 一例ですが、
一例ですが、
今回のDay4課題の基となったデザインは
”キーワード”をもとに制作しております
「塾生向けの東京勉強会(抽選)」のキーワード中で
①「塾生向け」の優先順位を上げるパターン
②「抽選」の優先順位を上げるパターン
③「勉強会」の優先順位を上げるパターン
④「東京」の優先順位を上げるパターン)
4つに分類し内2パターン作った結果、最終的に2案とも没、
クライアント=尾上講師の要望で
①の優先順位を高めたデザインが選ばれました
![]() 3案は基本的にバナー、LP、HP等いたる制作物で必要です。
3案は基本的にバナー、LP、HP等いたる制作物で必要です。
厳格に3案ではなく、
・クライアントとの前提&認識合わせ
・デザインイメージの共有
ができている場合2案で決めることもあります。
3案、とお伝えしているのは
1案目:クライアントの要望を反映したデザイン
2案目:クライアントの要望を反映したうえで1案目と別パターンのデザイン
3案目:クライアントの前提条件を理解したうえで
デザイナーとしてより良くなるプロとしての提案を踏まえたデザイン
とした方がクライアントも納得感を持って選択&決裁できる
という意図があります。
ただし、LPやHPは提案時全体を制作するのではなく
LPの顔となるFV(ファーストビュー)部分を3案制作します。
FVのデザインが問題なければFVのデザインに沿ってLP全体を
仕上げるためクライアントとの認識も大きくズレず
すべて作り直し、手戻りがない=双方の時短にもなるからです。
![]() はい、47都道府県すべてLPを変えたり、反応の良いLPが見つかるまで複数デザイン回しているので50LP以上は試してます。
はい、47都道府県すべてLPを変えたり、反応の良いLPが見つかるまで複数デザイン回しているので50LP以上は試してます。
もちろん経験は役立ちますが、時期や対象が変わればデザインもレターも変わるのでLPだけでなく広告の文言等も数を打って決めることもあります。
基本的に人は「見ない、読まない、信じない、行動しない」です
3秒で離脱する(=3秒ルール)ことを前提に
LP全体を一新することよりもFVを何度も変えて試すことが多いです。
![]()
何を調査したいかにもよりますが他にも分析方法やツールはあります
大きく分類すると5つほど分析ツールがあり
一番有名な分析方法は「顧客アンケート」です。
どのツールを使うかは、分析の目的によって変わります。
ユーザー行動の追跡、コンバージョン率向上、SEO改善など、
何を重点的に分析したいかを決めてから選ぶとよいでしょう。
1. 定量分析ツール
サイト訪問者の行動を詳細に分析できるツール。
ユーザーの流入経路、滞在時間、離脱率など
2. 定性分析ツール
訪問者の行動を録画して、どのようにページを操作しているかを確認
スクロールマップやクリックトラッキングも可能
3. SEO・検索トラフィック分析
検索流入のデータを分析し、改善点を把握
キーワード分析や広告運用の最適化も可能
4. A/Bテストツール
異なるバージョンのページをテストし、コンバージョン率が高いデザインを特定
直感的なUIでどちらがいいかを判断
5. カスタマーサポート・フィードバック分析
アンケートをとり、ユーザーから直接フィードバックを
収集して分析し、アンケートをとり、ユーザーから直接フィードバックを収集して分析するものなどがあります。
![]() Clarityを入れて管理者にエラーが出る等の影響はないですが、自社のサイトにこっそり入れて情報収集する等はNG。会社の規定に従いましょう。
Clarityを入れて管理者にエラーが出る等の影響はないですが、自社のサイトにこっそり入れて情報収集する等はNG。会社の規定に従いましょう。
![]() ボタンに影を真下(90°)に入れる理由は、「押せる場所」だと一目で伝えるためです。
ボタンに影を真下(90°)に入れる理由は、「押せる場所」だと一目で伝えるためです。
現実世界の光は上から(太陽や照明)当たることが多く、影は下に落ちるのが自然
そのためWeb上でも影を下に入れると、立体感が出て、押せるボタンに見えやすくなる
Webページは上から下へスクロールする構造なので、下方向の影は動きとも調和するので〇
※人は違和感を感じると行動を止めるため自然/調和はデザインでも大切です
※目に留める際、違和感は有効ですが申込で行動を止めるのはNG。致命的になることがあります
【補足】Webボタンのルーツは電話機のボタンと言われています。
まだWebが普及していない際、
「どうしたら(まだ普及していない)Web上で、
画面上でも”ここは押せます、ここから物を買えます”」と
気付いてもらえるか、わかってもらえるのかと模索した結果、
みんなが知っている電話に立ち返り、普及しました。
電話のボタンも右下に影がつくのでその名残で
右下に影がついたもの=押せるもの=ボタンとして現存してます。
今はWebが普及してインタラクションデザイン(動的なデザイン含む)で色が変わったり、
マウスオーバーで動いたもの=ボタンと認知されてたり、四角で囲えばボタン、下線があればボタン…と
Webボタンの認知が広がるにつれシンプルなボタンにデザイン&遊び心をいれることもできるようになりました。
![]() ①価格を上げる理由を明確にする
①価格を上げる理由を明確にする
実例:お見積もりの際に価格の内訳、割引理由を明記しておく
▼【お見積り】
概算:¥5,000-
【内訳】
基本¥5,000(5分以内)×1本
→カット作業、SE・BGM挿入、画像挿入、文字の装飾、テロップ挿入含む
※通常10,000円ですが10名限定キャンペーンで5,000円引きです
キャンペーン適用人数外、期間外のため
正規料金で対応等は明記しておくことで
価格に納得いただける可能性が高いです
現在価格の内訳、定価等を定義していない場合は
先ず定義を明記するところから始めましょう
(独自のキャンペーンを用意しておくことで値上げの
伏線を打つことができるのでお勧めです)
② 価格アップ後のメリットを伝える
➤今まで制作だけで終えていたものをヒートマップ分析を導入し、解析&改善までサポートする…など
相手のご希望に沿った提案をすることで、値上げの正当性を伝えることもあります。
*クライアントが求めていない理由付け=自己都合での
値上げはリピーター離れになるのでNGです
🔻実際の事例:15万円の案件を35万円(+20万円)の値上げに成功した際の提案資料
➤値上げに失敗した例:
デザイナー「スキルアップでクオリティ上がったので…」
クライアント「正直言って、現在のクオリティで問題ないので価格そのままで対応してくれませんか?」
リピーターがなぜあなたに依頼しているか
分からない場合は、アンケートを導入してクライアントの意図を知るところから始めてみましょう。
![]()
はい、挑戦できるものはぜひ挑戦してみてください。
クライアントの評価、採用の理由まで確認でき
学びになります。
前提条件も掲載されているのでポートフォリオに
掲載する自主制作の架空テーマ設定にもおすすめです。
🔻事例
https://crowdworks.jp/public/jobs/11458665
🔻前提条件をまとめて
力試しの100本ノックをされるデザイナーさんもいます
ココナラをお勧めしている理由は
案件を受注する際、
クラウドソーシングサイトの中でも
競合もデザイン初心者~中級者になるため初心者
デザイナー向けだからです。
学びを得るという点ではクラウドワークスの方が
レベルが高いため自習としてクラウドワークスを
使うこともあります。
![]() 1ページ完結型のランディングページについては、
1ページ完結型のランディングページについては、
案件により必要な場合も有ります。
企業のホームページ・コーポレートサイトについてはSEO対策が必要です。
また、実店舗の場合は、SEOに限らずMEOの知識も必要になってきます。
![]() どの範囲までカバーできるかという視点であれば 幅広くAIを活用できます。
どの範囲までカバーできるかという視点であれば 幅広くAIを活用できます。
デザインレベル関してのAIのお話でしたら できは4~6割の印象です。
クライアントに提示するイメージ作成を時短するため 資料の一部に使うことはございますが そのまま納品するレベルには至っていません。
![]() 行ける範囲であれば直接行きましょう。クライアントに会いに行く際はお菓子等も持参すると好印象です。(フリーランスデザイナー=社会人経験が少なく、一般常識がないと思っているクライアントも少なくありません。返報性の法則でいうなら、何かを渡すことで案件がスムーズに運ぶこともあります)
行ける範囲であれば直接行きましょう。クライアントに会いに行く際はお菓子等も持参すると好印象です。(フリーランスデザイナー=社会人経験が少なく、一般常識がないと思っているクライアントも少なくありません。返報性の法則でいうなら、何かを渡すことで案件がスムーズに運ぶこともあります)
相手の好みが分からないときは「ヨックモック」がオススメ。
*嫌いな人あまりいないのでハズレません
*デザイナーの中には手紙を添えたことで「久しぶりに人から手紙をもらって嬉しかった」とリピートに繋がった例も
尾上の経験上、年配のクライアントにはどら焼きが結構好まれたので参考までに。
![]() 現在他の案件で立て込んでいましてお受けできません」
現在他の案件で立て込んでいましてお受けできません」
「お先に受けた案件と納期が重なっており…」と断ってます。
わざと通常料金より少し上乗せして予算とあわせないようにしたりすることも時にはあります。
初案件等、実績がなければ断らないことも大事ですが
実績や実力がある人は地雷案件を踏まないよう見極めて断ることもしばしば。
着手後なら
やむを得ない諸事情があり(内容はときによって変わります)継続困難になったため、
ということで「謝罪&今まで進めた分のデザインデータプレゼント&
全額返金or代わりの人を紹介で打診」して対応したデザイナーもいます。
![]() 初案件の方は1件ずつの方が流れも分かるので丁寧にやっていきましょう。
初案件の方は1件ずつの方が流れも分かるので丁寧にやっていきましょう。
2件、3件と慣れてくると返答にある程度テンプレが使えるようになったりデザイン制作速度も上がり同時進行もできるようになるため慣れてから同時進行で進めていくことがオススメ。
*同時進行NGでよくあるミスはもう一方の案件データを間違えて渡すなどです。情報漏洩で信用問題になるので案件管理シート等で進捗やデータを管理するのがプロの基本
![]() 店舗デザインをしたときはLP、制服(アパレル)、チラシ、ゴルフクラブのヘッドやシャフト等のデザイン、書籍までトータルデザインしてフォローしたので信頼関係で値切られたりしないです。
店舗デザインをしたときはLP、制服(アパレル)、チラシ、ゴルフクラブのヘッドやシャフト等のデザイン、書籍までトータルデザインしてフォローしたので信頼関係で値切られたりしないです。
「早くできるなら安くしろ」というクライアントはデザイナーを人だと思ってないので早めに縁を切りましょう。
![]() ご自身でデザインができ、デザインの判断基準があったうえで「今回は”時短のためにあえてテンプレートを使っている」なら問題ないです。
ご自身でデザインができ、デザインの判断基準があったうえで「今回は”時短のためにあえてテンプレートを使っている」なら問題ないです。
クライアントの要望に応える上で、テンプレートだけでは解決できないことの方が多いです。
「簡単お手軽に作れる、楽に稼げる」からテンプレートを使っているようであれば低単価デザイナーで終わります。
![]() どこでどう回すか、誰に見てもらうつもりなのか含めヒアリングを大事にしてます。
どこでどう回すか、誰に見てもらうつもりなのか含めヒアリングを大事にしてます。
制作よりも顧客の売り上げ貢献をできるLPかどうか含め、数字に着目はマスト。
作って終わりではなく自分が作ったLPがどう活躍するか、育てるところまで想定して制作しています。
![]() Day1の課題提出後に受け取れる特典01の
Day1の課題提出後に受け取れる特典01の
「Webデザイン1年生のための教科書」を ぜひご覧ください。 今回のチャレンジで学んだことの復習にもなります。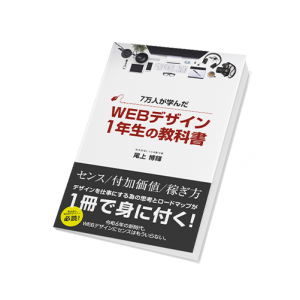
基礎を学んだあとは、 初心者こそ「やってはいけないデザイン」を学ぶと 理解が深まります。
▼おすすめ書籍
・ノンデザイナーズ・デザインブック(Robin Williams)
・やってはいけないデザイン(平本 久美子)
・なるほどデザイン(筒井 美希)
※外部書籍のため、
内容に関するお問い合わせはご遠慮ください。